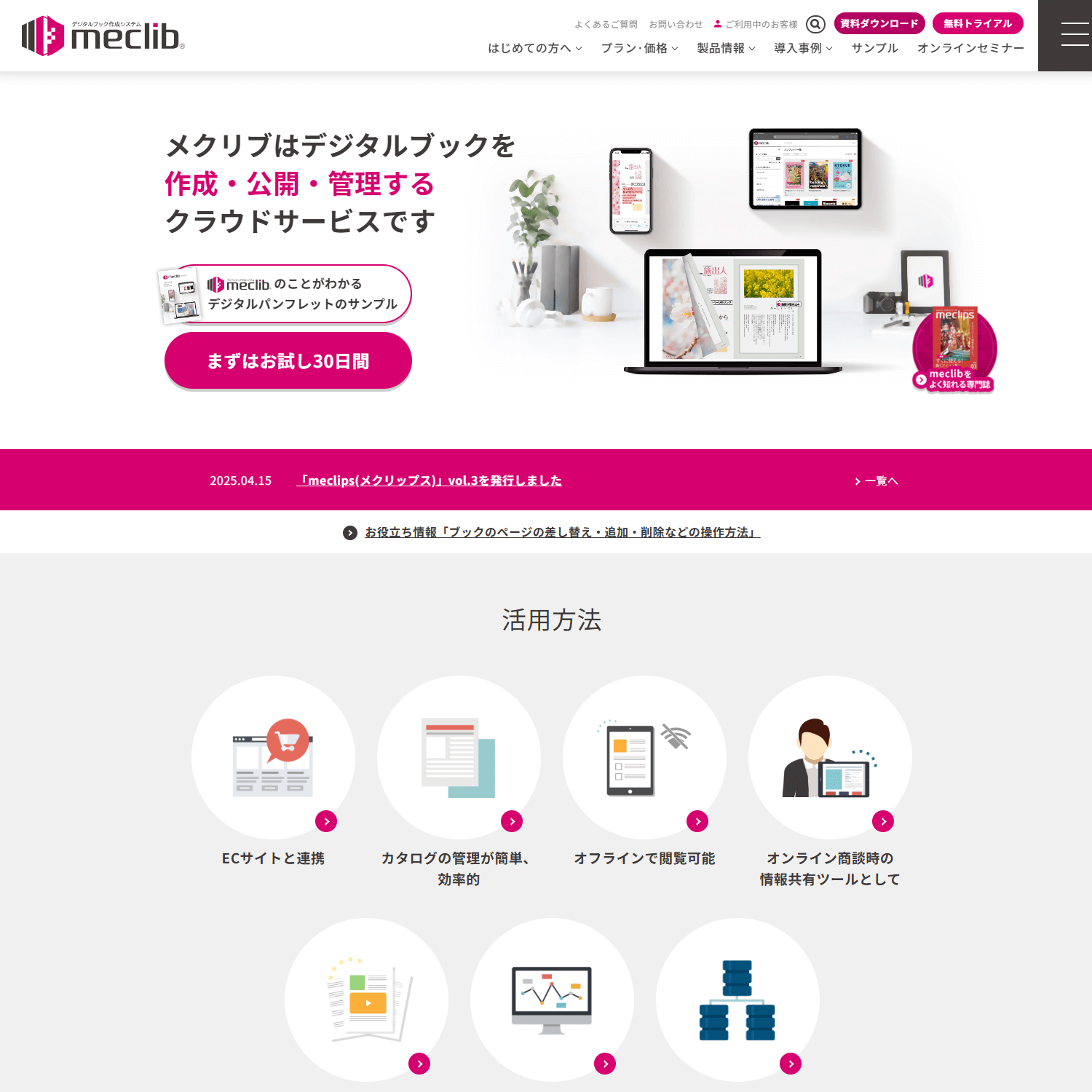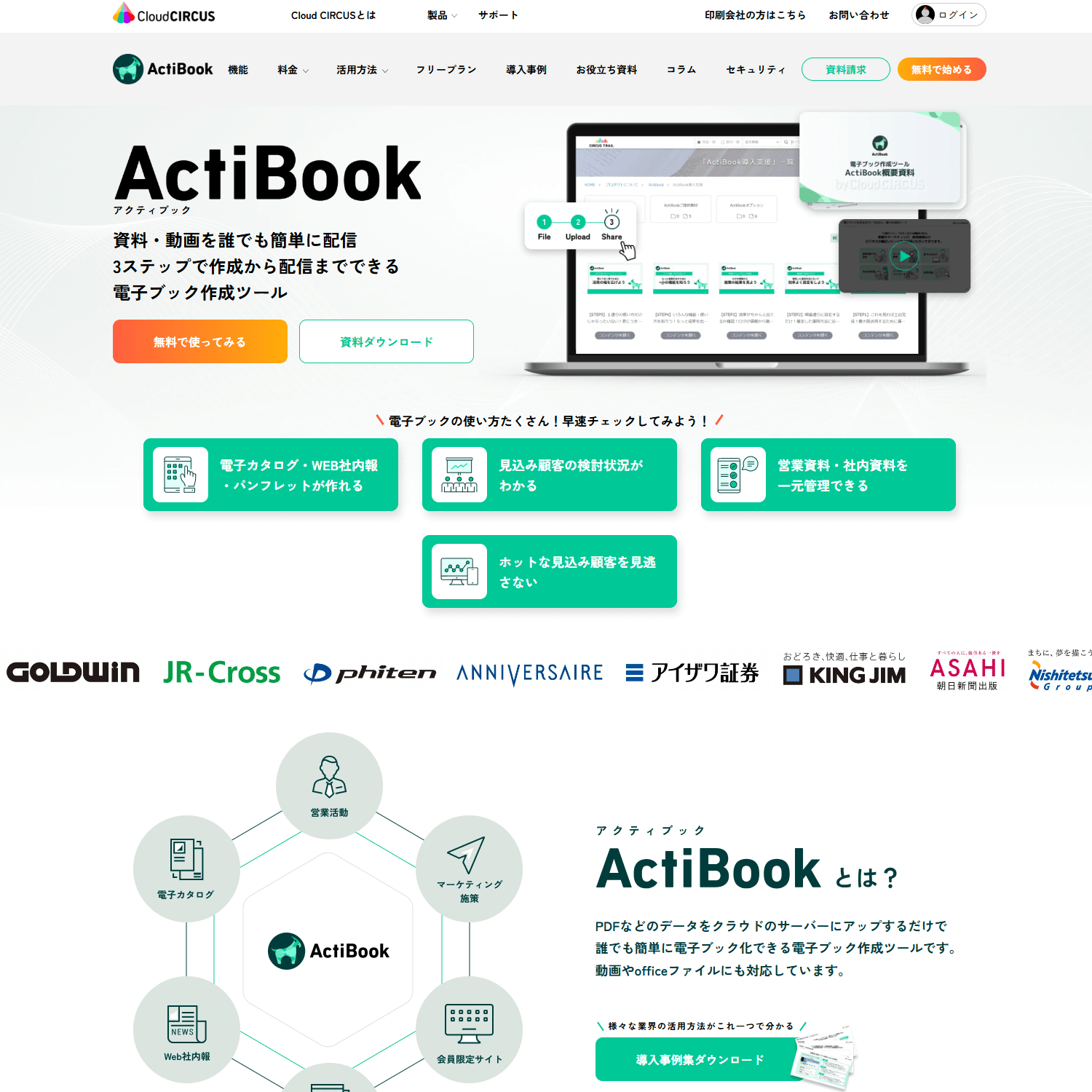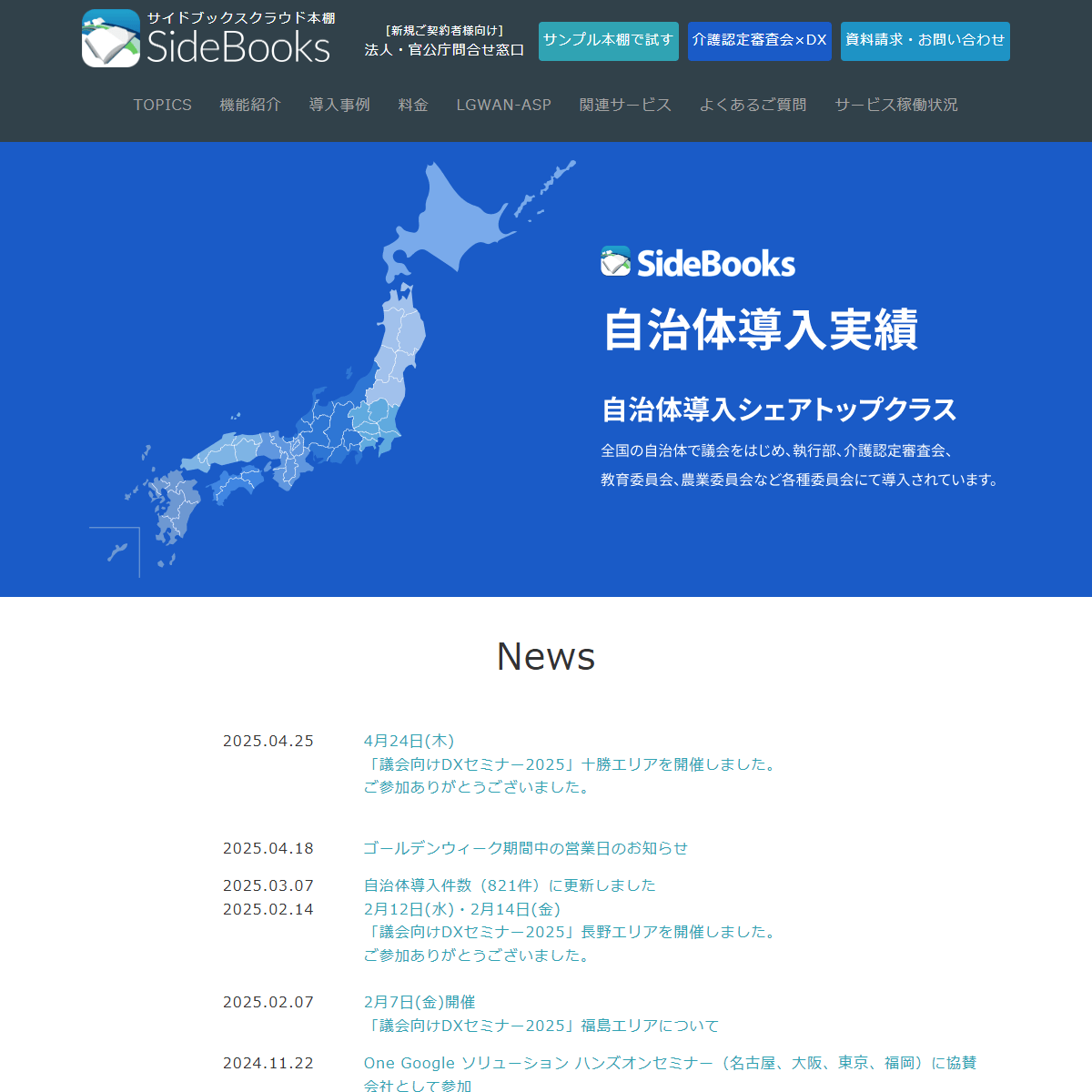2024年度から小中学校で本格的に導入が開始されたデジタル教科書。紙の教材や教科書との併用を前提として導入されており、紙の教材にはないメリットが存在します。本記事では、デジタル教科書・デジタル教材とは何かについて詳しく紹介していきます。詳しい機能やメリット・デメリットについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
デジタル教科書とは?
デジタル教科書・デジタル教材と聞いても、具体的にどのような物を示すのかわからない人もいるでしょう。そこでここでは、デジタル教科書・デジタル教材の定義と普及率について紹介します。具体的なイメージがわかないという方は、ぜひ参考にしてください。デジタル教科書・デジタル教材の定義
デジタル教科書・教材とは、タブレット端末などから見られる電子化された教科書・教材のことです。デジタル教科書・教材には、教員向けに開発されたものと生徒向けに開発されたものの2タイプが存在し、教員向けのデジタル教科書・教材はプロジェクターや電子黒板での使用に適しています。デジタル教科書・デジタル教材の普及率
文部科学省が公表している第1回デジタル教科書促進ワーキンググループの資料によると、2025年時点の学習者用デジタル教科書の発行割合は、小学校が100%、中学校が99%、高等学校が76%とされています。高等学校では令和4年度から発行割合が80%未満のままですが、小学校と中学校では100%近い発行割合となっており、今後はより普及していくと考えられます。なお、デジタル教科書は大きく普及が進んでいるのに対して、デジタル教材はまだまだ公的な教育機関での普及率は高くありません。
デジタル教科書とデジタル教材の違い
デジタル教科書とデジタル教材は名前が似ていますが、教育分野では教科書と教材は全くの別物として明確に分類されています。教科書とは、文部科学省の検定に合格したもののことで、教材とは教科書での学習をサポートするための補助的な役割を負うもののことです。つまり、授業を進める上でメインに使用される書籍が教科書に該当し、学習に必要不可欠なノートやプリント、参考書、実験器具などはすべて教材に該当します。
デジタル教科書・教材の主な機能と活用方法
次にデジタル教科書・教材の主な機能と具体的な活用方法を紹介します。デジタル教科書・教材には、文字の拡大や音声・動画の再生、書き込み保存などの紙媒体にはない機能があります。これにより、学習意欲の向上や対話的な学習を取り入れやすくなること、学習への理解が深まることなどの効果が期待可能です。
学習意欲の向上
デジタル教科書・教材では、紙媒体では不可能な動画や音声を取り込むことが可能です。教科書に書かれた文字を目で追ったり、教師の話を聞いたりするだけでは飽きてしまうような内容でも、動画やプロの朗読音声といったデジタル教科書・教材ならではの機能を活用すれば、興味を引きやすくなります。対話的な学習を取り入れやすくなる
デジタル教科書・教材では、紙媒体よりも教科書への書き込みが簡単に行えるので、今までノートに教科書の内容を書き写していた時間を大幅に短縮できます。書き写す作業の短縮に成功できれば、今まで以上に考えたりグループで話し合ったりする作業に時間を割けるようになり、対話的な学習が取り入れやすくなるでしょう。
デジタル教科書のメリット・デメリット
最後に、デジタル教科書・デジタル教材のメリットとデメリットをまとめて紹介します。デジタル教科書・デジタル教材には、紙の教科書・教材とは異なるメリット・デメリットがあるので、導入を検討する際は長所と短所の両方の側面を把握した上で判断することが大切です。教員の負担が減る
デジタル教科書・教材のメリットとしては、まず教員の負担が減らせることが挙げられます。従来の紙媒体中心の授業では、教材資料の作成に多くの時間がかかっていましたが、デジタル教科書・教材であれば、資料の追加や編集が簡単に行えるため教材資料作成の負担軽減が期待できます。荷物の軽量化に繋がる
デジタル教科書・教材を導入すれば、今まで複数あった教科書や教材が1つのタブレット端末に集約されるため、荷物の軽量化に繋がります。小学生のランドセルが重すぎるという現状はこれまでも度々問題視されてきた課題の1つです。日々たくさんの教科書や教材を持ち歩く必要のある生徒・学生にとっては、荷物の軽量化に繋がることは大きなメリットであると言えるでしょう。
コストがかかる
デジタル教科書・教材の最大のデメリットは、コストがかかることでしょう。紙の教科書や教材であれば、紛失したり壊したりしても新しい物を用意するのにそれほどの費用は掛かりません。しかし、デジタル教科書・教材を見るためのタブレット端末は、紛失したり壊れてしまうと1回で数万円前後の費用がかかることも珍しくありません。
学校単位で保険に加入していれば保護者への負担はかかりませんが、保険の加入が個々の判断に委ねられた場合は、壊した端末を再度用意できないという家庭も発生する可能性があります。
視力の低下に繋がる可能性がある
デジタル教科書・教材には、視力の低下に繋がる可能性があるというデメリットも存在します。タブレット端末の画面から発せられる光を長時間見続けると、眼精疲労や視力の低下、ドライアイに繋がる恐れがあると言われています。紙の教材や教科書を使用すれば絶対に視力の低下に繋がらないという訳ではありませんが、デジタル教科書・教材を導入する際は、適度に目を休められる時間を確保することが大切です。